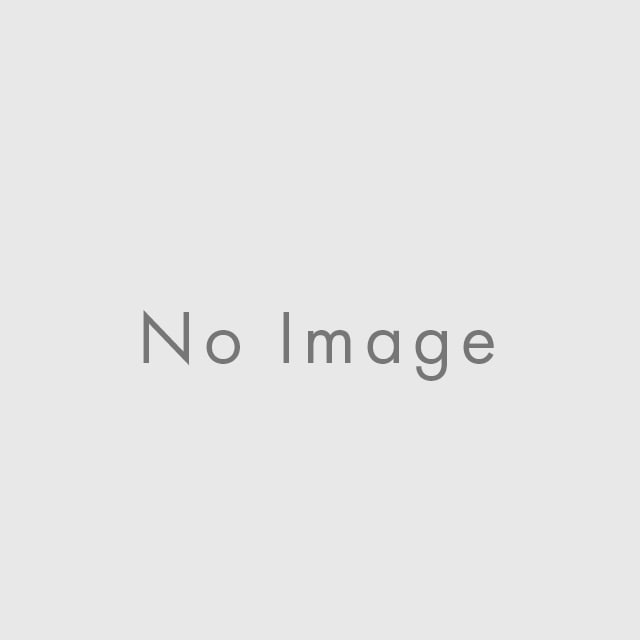目次
季節の変わり目や風邪が流行りやすい時期に、ふとしたきっかけで流行するのが溶連菌感染症です。典型的な症状であれば早期発見が可能ですが、症状がそろわないとただの風邪としてみられてしまい、園や学校で流行してしまうケースも少なくありません。溶連菌は一度かかったからといって免疫がつくわけではないため、何度も感染する病気です。
溶連菌感染症とは?
溶連菌感染症は、A群溶血性レンサ球菌(溶連菌)という細菌が喉に感染することで発症する感染症で、特に子どもたちに多く見られ、5歳〜15歳が最もかかりやすいとされています。溶連菌感染症は喉の痛みを引き起こすだけでなく、発疹や高熱、全身の倦怠感といったさまざまな症状を伴います。細菌が原因であるため、抗生物質による治療が必要です。
溶連菌感染症の主な症状・診断法
溶連菌感染症の典型的な症状は、急に喉が痛くなることです。その他にも以下のような症状が見られることがあります。
・発熱
38℃以上の熱が出ることが多く、特に初期症状で高熱が続くことがあります。数日で解熱することが多いですが、常在菌として喉に定着してしまい再発することもあります。
・喉の痛み
喉が非常に痛くなり、特に飲み込むときに強く痛みます。風邪に伴う喉の痛みとは異なり、激しい痛みが出ることが特徴です。
・発疹やイチゴ舌
子どもの体に小さな赤い発疹が出ることがあります。また、舌がイチゴのように赤く腫れてブツブツした状態(イチゴ舌)になることも特徴です。
・白い膿や赤く腫れた喉
喉を見てみると、赤く腫れた扁桃腺や白い膿が付着していることがあります。
これらの症状がいくつか出れば溶連菌を疑い検査を行います。のどに綿棒をこすり溶連菌を捕まえる検査で5-10分で結果が出ます。
溶連菌感染症の治療法
溶連菌感染症は、細菌が原因であるため、ウイルス性の風邪とは異なり、抗生物質での治療が必要です。
・抗生物質の服用
溶連菌感染症の治療には、ペニシリン系の抗生物質が一般的に使用されます。通常、抗生物質を10日間ほど服用し、感染を完全に根絶させることが重要です。途中で服用をやめると、再発したり、合併症を引き起こす可能性があるため、医師の指示通りに最後まで薬を服用することが大切です。10日間飲むのが難しい場合や何度も溶連菌を繰り返す場合には他の抗生物質を選択することがあります。かかりつけの先生に相談してみてください。
・症状が改善しても注意
抗生物質を服用すると、通常24〜48時間で症状が改善します。熱が下がって丸一日様子見れば登園登校は可能です。
合併症のリスク
溶連菌感染症は、適切な治療を行わないと重篤な合併症を引き起こすことがあります。特に注意すべき合併症には以下のようなものがあります。
・急性糸球体腎炎
溶連菌感染症の後に、腎臓に影響を与えることがあります。
溶連菌感染後3-4週間後くらいに血尿やむくみ、高血圧などの症状が現れることがあります。
血尿が出て病院を受診したら、過去の溶連菌感染症が分かったというケースもあります。
・リウマチ熱
溶連菌に対する免疫反応が体の他の部位に影響を与えることで発症します。
特に心臓や関節、脳に問題を引き起こすことがあり、発症すると長期的な治療が必要です。
どんな時に受診が必要か?
溶連菌感染症は、早期発見と適切な治療が重要です。以下のような症状が見られた場合は、医療機関を受診しましょう。
・突然の高熱と喉の痛み
喉が急に痛くなり、同時に38℃以上の高熱が出た場合。
・発疹やイチゴ舌が見られた場合
体に赤い発疹が広がったり、舌が赤くブツブツした状態になった場合も、溶連菌感染症かもしれません。小児科医に相談してください。
園や学校で流行していて上記の症状があれば診断しやすいのですが、流行がなく、症状が発疹だけの場合は診断が遅れてしまうこともあります。
また、ご家族に溶連菌感染症の方がいて、お子さんに感染するケースも多いです。
ご両親で体調不良時にのどが痛くなることが多い場合には、溶連喫感染を疑ってみてください。
溶連菌感染症の予防法
・手洗い・うがいの徹底
外出先から帰ってきた時や食事の前後、トイレの後には必ず手洗い・うがいを徹底しましょう。
・マスクの着用
飛沫感染を防ぐために、人が多い場所ではマスクを着用しましょう。
・家庭内の消毒
家庭内で感染者が出た場合、ドアノブやおもちゃ、リモコンなど、よく触れる場所を消毒することが大切です。また、感染者が使用したタオルや食器などは、他の家族と分けて使用するようにしましょう。
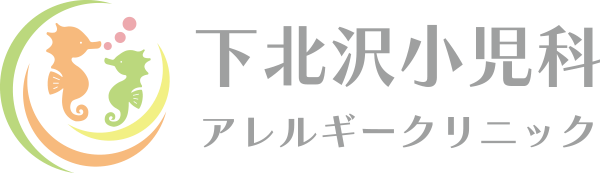
 WEB予約
WEB予約